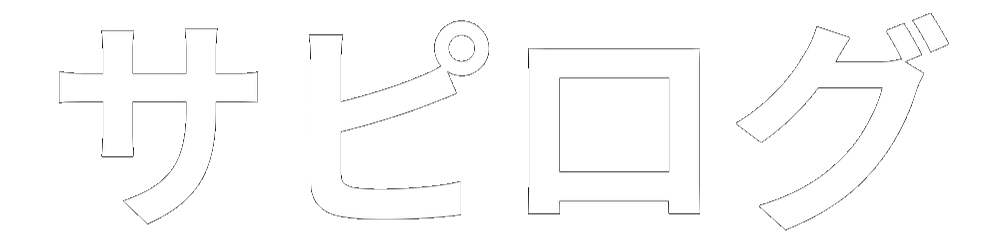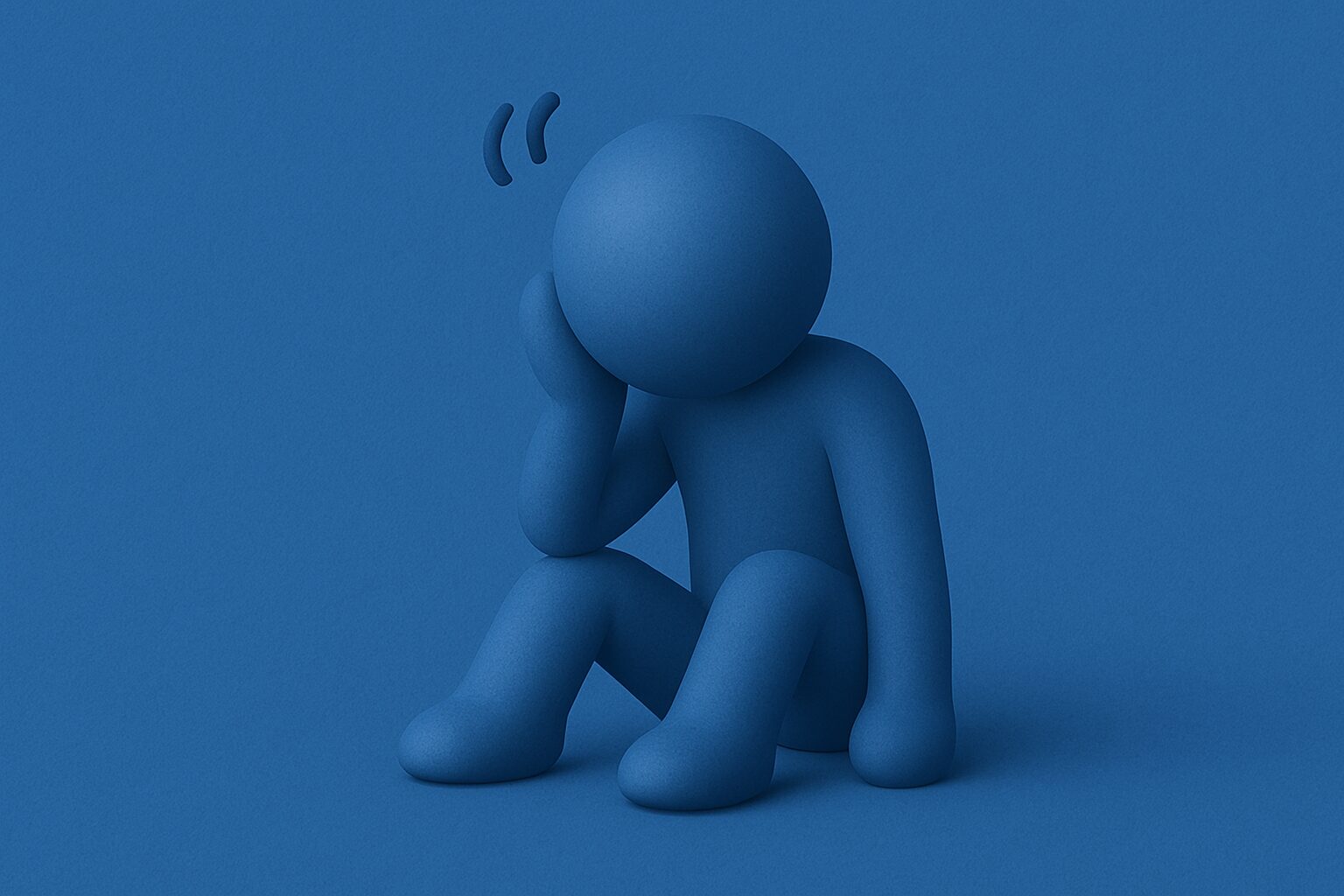SAPIXの国語デイリーチェックとは?出題内容や家庭での対策
国語デイリーチェックの対策法・返却後にやるべきこと
デイリーチェックとは
4年生以降の各授業で行う復習テストがデイリーチェックです。
国語のデイリーチェックはA授業の冒頭で行い、語彙や漢字などが出題されます。
テスト終了後は「回収して講師が採点→翌週に返却」が基本の流れ。
長期休み前など一部の場合、授業中に交換採点を行います。

国語デイリーチェックの出題内容
| 出題内容 | 範囲 | 4年生の配点 | 5年生・6年生の配点 |
|---|---|---|---|
| 漢字 | 前回テキスト | 50点 (5点×10問) | 40点 (2点×20問) |
| 文法 | 知の冒険 | 25点 | 30点 |
| 語彙 | 言葉ナビ | 25点 | 30点 |
なぜ重要?国語デイリーチェックの目的と意義
言うまでもなく、デイリーチェックの意義は「国語の土台作り」です。
入試問題で頻出の漢字や語彙はもちろんのこと、手紙の書き方や敬語などの知識事項も網羅しています。基礎力重視のA授業の中で、要となるのが国語のデイリーチェックなのです。
国語デイリーチェックを家庭で対策するときのポイント
複数回に分ける
年間学習法や保護者会でも言われることですが、デイリーチェックの勉強は複数回に分けることが対策法としての王道です。たとえば、毎週水曜日に国語の授業があるなら…
- 木曜日:前回の復習+漢字(1周目)
- 土曜日:漢字(2周目)+文法・語彙
- 火曜日:漢字(3周目)+文法・語彙
- 水曜日:最終チェック
のように、1日30分×3回程度に分けて勉強しましょう。
間違いやすい問題に絞る
勉強する中で、間違えた問題には★マークを残しておきます。
繰り返し勉強すると★がどんどん増えていき、自分が間違えた回数が可視化されます。★の多い問題を重点的に復習すれば、勉強効率を上げられます。
コアプラス等でも推奨される勉強法。高得点の生徒がよく実践しています。

「書けば覚える」ではなく「覚えるために書く」
基本は、書いて覚える生徒が多いです。
しかし、同じように書いても正しい漢字が覚えられない子は多い。原因は、漢字を書くこと(漢字練習帳を埋めること)自体が目的になっていることにあるようです。「覚えるために書く」という意識が子どもにない限り、なかなか高得点にはつながりません。
たくさん書いても覚えられない子は、あえて練習回数に上限を設けるのも手です。
「今週はテストまでに同じ漢字を●回までしか練習してはいけないルール」を設定し、ゲーム感覚で「覚えるために書く」という意識を持たせましょう。
漢字練習に「工夫の余地がある」と考えさせることが重要です。

相性のいい勉強法を探す
そもそも「何回書いても覚えられない!」という子もいるはずです。
どの方法が覚えやすいかは子どもによってバラバラ。書いて練習することにこだわりすぎず、自分に合う方法を探すことが大切です。
- 新しい語彙や漢字で例文を自作
まずは辞書にある用法を書き写すところから始める - 忘れやすい語彙や漢字を一冊のノートに集約
几帳面タイプにおすすめ、テスト前の復習にも便利 - 新しい語彙や漢字を普段の会話に取り入れる
聴覚優位の子は「話す」「聞く」を増やしてみる
国語デイリーチェックの返却後にやりたいこと
返却後は間違い直しをするのが鉄則ですが、もう少し踏み込んで解説します。
90点以上(4年生は80点以上)の場合
ミスが4~5問なら「次に同じ問題が出たときに間違えない」レベルまで直します。
誤答箇所をノートに書き出すのでも十分ですが、できれば「なぜ失点したのか」次につながる対策を講じておきたいところです。たとえば…
| 自分の解答 | 正解 | 対策 | |
|---|---|---|---|
| 問2 | 武土 | 武士 | 似ている字があるときはハッキリ区別する |
| 問3 | 収める | 納める | 両方の意味を調べて違いをまとめる |
| 問5 | 主観↔○観 | 主観↔客観 | ★マークのある問題はテスト直前に再確認 |
マンスリー対策にも使える、自分だけの対策ノートが出来上がります。

90点未満(4年生は80点未満)の場合
ミスが5個以上あるなら、まずは最も失点の少ない分野に絞って直しましょう。
失点が多い分野の方が(伸びしろは大きいので)直しを優先したくなりますが、その分だけ時間がかかる。時間がかかるほどモチベーションが下がる可能性があるので、だったら短時間で終わる分野を優先すべきだというのが私の考えです。
漢字・語彙・文法、どれかひとつでも「得意だ」と思えれば、他を底上げするのは案外スムーズに進むものです。

国語のデイリーチェックで基礎力を強化しよう
基礎だからといって侮れないSAPIXの国語のデイリーチェック。
対策そのものが得点へ直接結びつくだけでなく、読解問題を正しく読んだり要点を押さえた記述答案を作ったりする基礎になります。日々の積み重ねを習慣化し、自信を持って入試本番に臨める国語力を育てましょう。