【座談会①】SAPIX夏期講習、小5サピ親の葛藤と変化

中学受験まであと1年半を切った小5の秋。
今回は、SAPIXに通う5年生の保護者3名にお集まりいただき、夏の過ごし方や学習リズム、家庭内のリアルな様子について本音で語ってもらった座談会の様子をお届けします。

参加者の紹介
今回の座談会には、SAPIXに通う5年生の保護者3名にご参加いただきました。(敬称略)
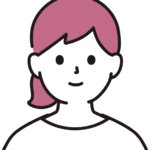
- 自身も夫も中受経験なし/中受サポートは夫と半分ずつ
- 情報収集はSNSがメイン
- 春から個別塾の併用をスタート
- 「親子そろってメンタルが不安定。けんかも日常茶飯事です」

- 自身は中受経験あり/妻は送迎と教材管理をサポート
- 情報収集はSNSや新聞・書籍など幅広く
- 個別塾の併用は検討中
- 「千里の道も一歩から。親のできることを日々考えています」

- 夫は中受経験あり/夫の中受サポートはほぼなし
- 情報収集はほとんどせず、塾頼り
- 個別塾の併用なし
- 「『目は離さないけど手は放す』がモットーです!」
夏期講習を終えた小5保護者の感想

本日はご参加ありがとうございます。ファシリテーターのコージです。
早速ですが、テーマは「小5親が語るSAPIXのリアルな夏」ということで、夏期講習の率直な感想をお聞かせください。
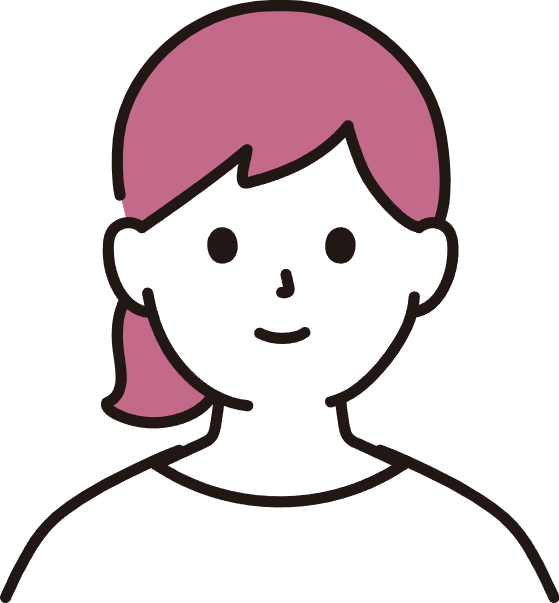
いや正直……大変でしたね(笑)
4年生のときより忙しくて授業も速くなってて…“できてる風”になってる怖さを感じてました。
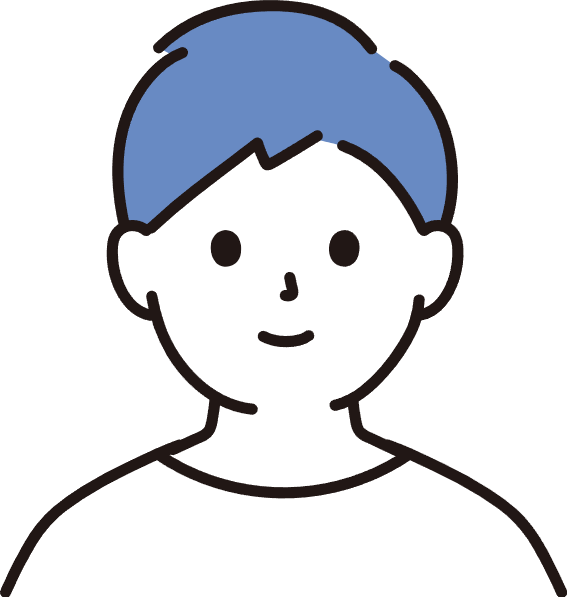
ある程度は計画していたので、うちは「想定内」でした。
ただ、さすがに連日だったので集中力には波があったので、そこは息子の様子を見ながらでしたね。講習で「この単元は強い」「ここは穴がある」っていう分析はできたので、そこは収穫でした。

私はね、せらママさんの逆で「思ってたより楽」でした(笑)
正直、去年の4年夏は地獄だったんですよ……毎日ケンカ。でも今年は逆に “諦める力”がついたというか(笑)

復習も「やれるとこまででOK!」って線引いたら、息子の機嫌も良くて意外とまわりました。とはいえ、苦手の理科はちょっと追いついてない感じしますね〜。兄のときも理社で苦労したんで、既視感ありました。
勉強を「やりなさい!」という代わりに

皆さん本当にお疲れ様でした。三者三様の感想ですね。
フジタさん、夏期のスケジュールを具体的に教えてもらってもいいですか?
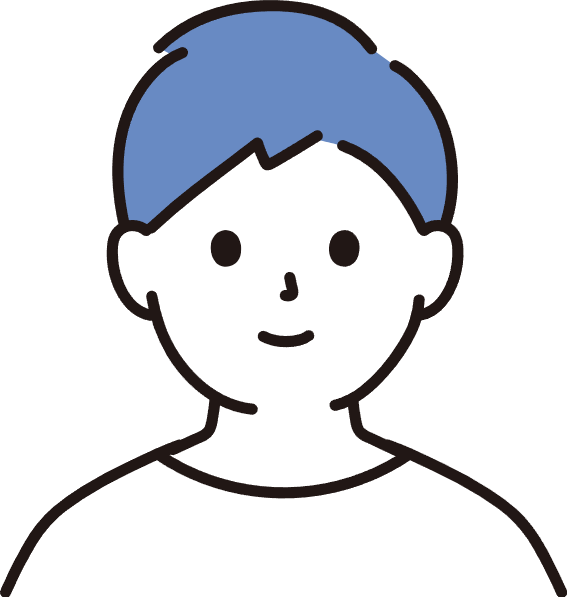
はい。基本的に午前中は授業、午後に復習、夜に科目ごとの過去単元の確認と軽い暗記って流れでした。息子にもタスクを見える化して、やったらチェックを入れるみたいな仕組みも入れてました。“勉強を仕事化”させるイメージです。

ひゃ〜〜!すごい!
計画…破綻するな、うちは絶対(笑)でも「勉強を仕事みたいに」って発想はなるほどって思いました。うちは「やる気がある日にやって、ない日は潔く寝る」っていう方針(?)で…。でもやる気がない日は大体ニガテな分野なので、差がエグいです(笑)
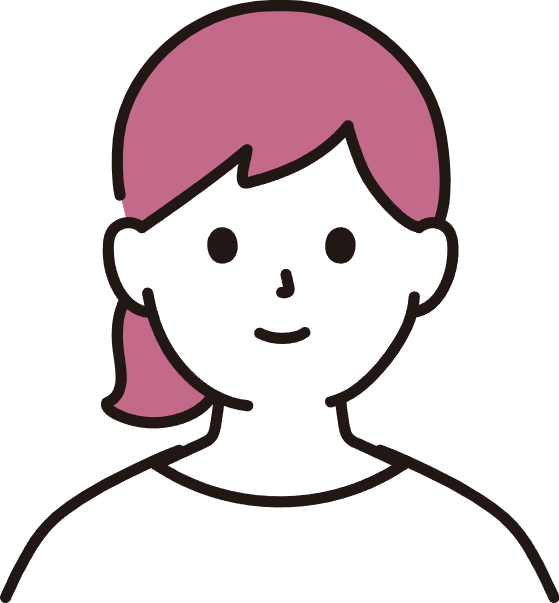
うちもれんママ寄りかも…(笑)
スケジュール管理っていうより、もはや火消し作業…。やっぱり“計画立てて先に動く”ってほんと大事なんですね…。
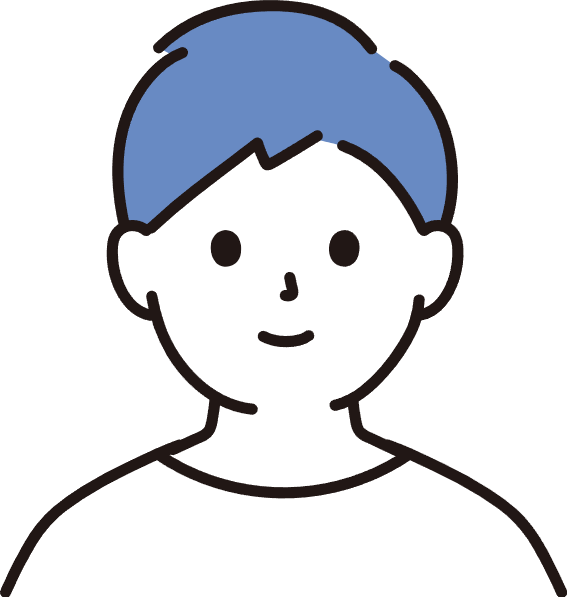
いやいや、うまくいったところだけ話してますから(笑)
実際はイレギュラーも多いですし、疲れてる日は切り上げることもありました。でも「復習はその日にやる」って線だけは守るようにしてましたね。

タスクを見える化すると感情論で勉強を押し付けることがなく、子どもの主体性が育めそうですね。参考にしたいです!
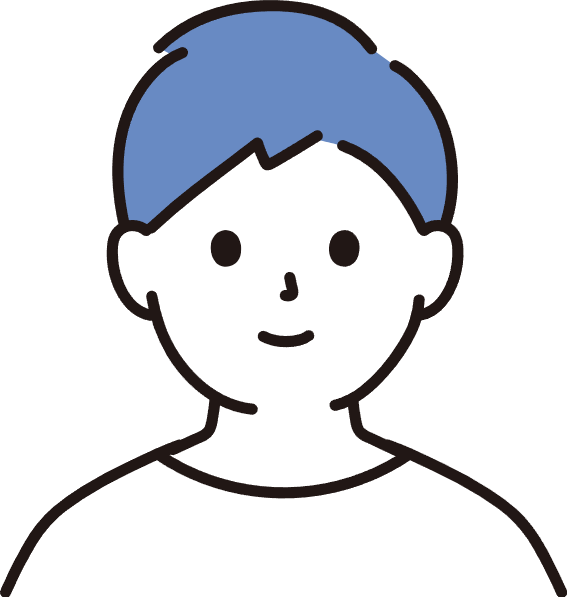
まさにそれが狙いでした。
「やりなさい!」って言う代わりに「今日のタスク、どこまでいけそう?」って“質問ベース”に変えるだけで、空気感が全然違うんですよ。
自分で付箋を動かしたり、できた項目を自分でチェックするだけでも、なんか“やらされ感”が減るんですよね。
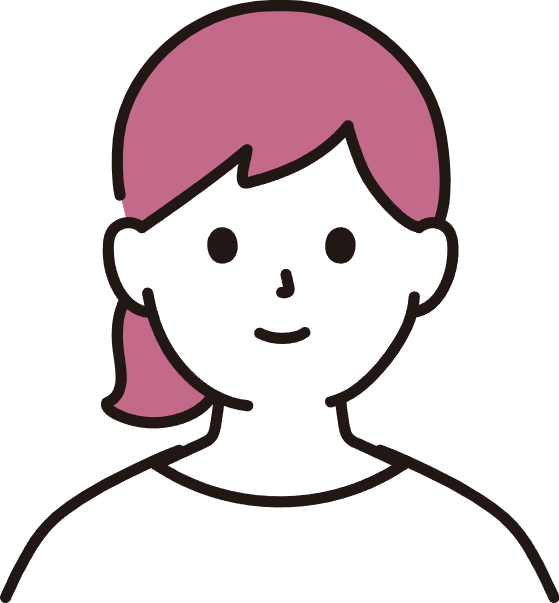
なるほど。うちは“主語が親”になっちゃってるんですよね…。「お母さんが言う前に勉強しよう」「お父さんが怒る前に終わらせなきゃ」みたいな。
今の話聞いて、「主語を子どもにする」って大事だな〜って思いました。

あ〜〜それ、ほんとそう!
でも夏の後半でちょっと変わったのは、「これ今やってる理由ってなに?」って息子に聞いたら、「だって復習しないとまたクラス落ちるじゃん」って返ってきて。
子どもって、自分の中で“理由がある勉強”は意外とちゃんとやるんですよね。
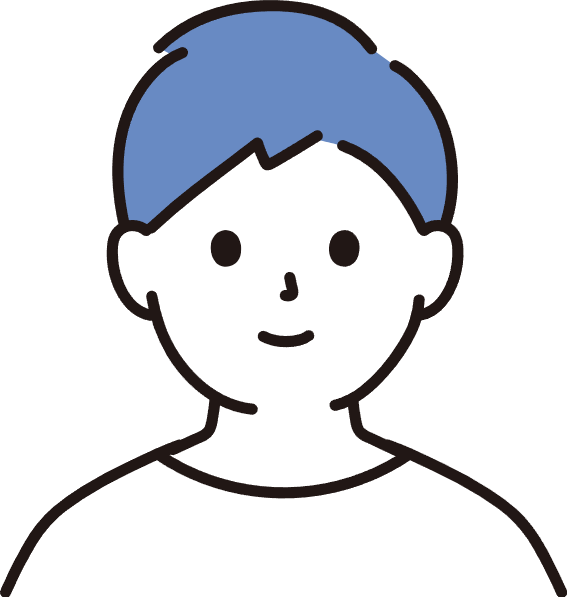
そうなんですよ。「なんでやるのか」を本人が理解してるかどうかで、全然違います。
親が管理しすぎると、理由じゃなくて“怒られないため”にやる勉強になっちゃうので…。
子どもにとっての「安心ゾーン」を作る

れんママさん・せらママさんは「家庭学習の声かけ」で工夫していることはありますか?

うーん、私はほんとに「声かけ」で失敗してきたタイプなので(笑)
上の子のとき、つい口出ししすぎて逆効果だったんですよね。だから今回はもう、“聞かれたら答える”スタンスにしてます。

あと意識してるのは「自分の言葉」で話させること。自分の言葉で感想とか考えを言うためには、きちんと理解する必要があるので。
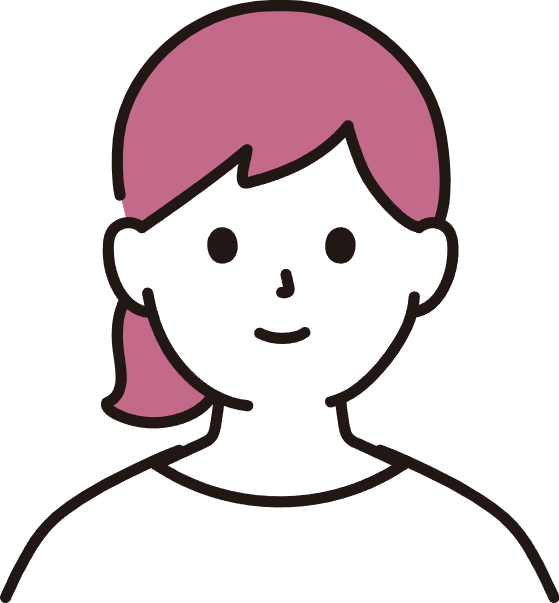
うちはどうしても「ここ違うよ」とか「それじゃダメじゃん」って指摘から入っちゃうタイプで…。
でも最近、個別の先生が“寄り添う言葉がけ”をしてるのを見て「ああ、こういう伝え方があるんだ」って衝撃を受けました。たとえば「ここちょっと惜しかったね、あと少しでできそうだよね」みたいな。
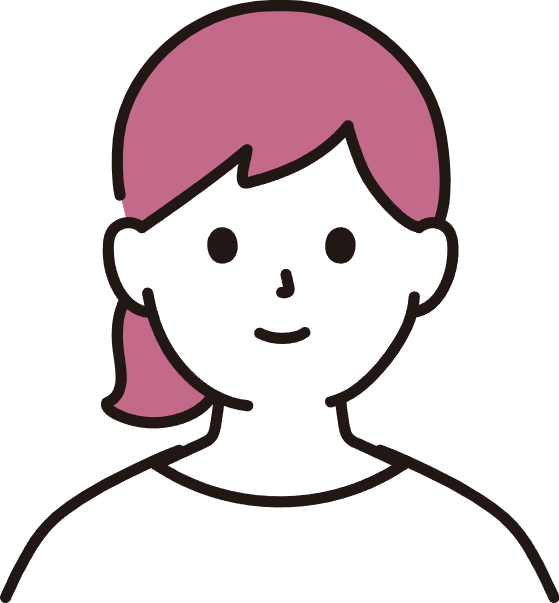
それを真似して「この問題、どこまで分かった?」って聞くように変えたら、本人も投げ出す前に自分で考えを整理して、前より話してくれるようになってきた気がします。
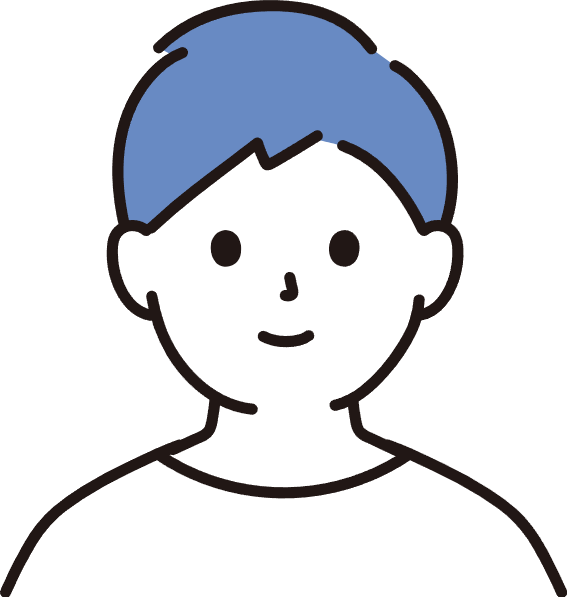
うちも一時期、言いすぎて息子が黙っちゃったことがあって、そこからあえて“聞かない時間”を作るようにしています。
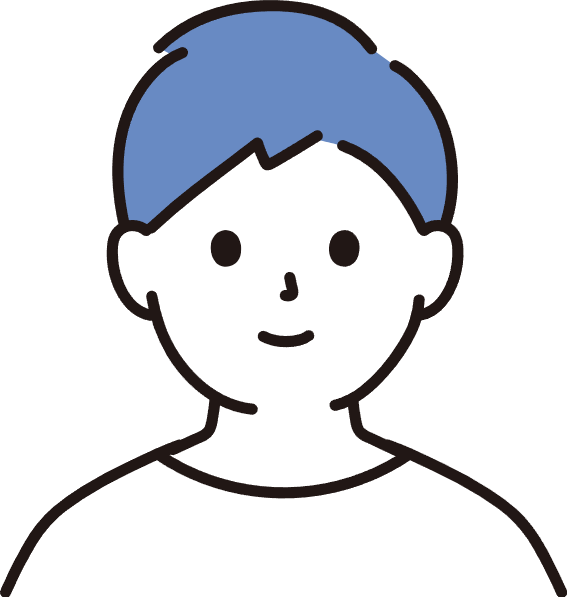
「お風呂では勉強の話はしない」とか、家の中にも“安心ゾーン”があるようにしてます。で、翌朝に「昨日の復習どうだった?」って軽く聞くと、意外と冷静に返ってきたりして。
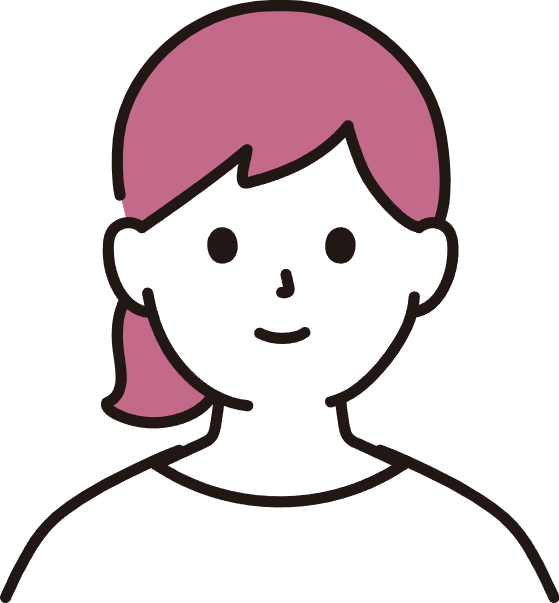
「安心ゾーン」いいですね!
完璧な計画よりも大切な「勉強習慣」

夏期講習で後悔していることや、夏期講習が始まる前の自分に教えてあげたいことはありますか?
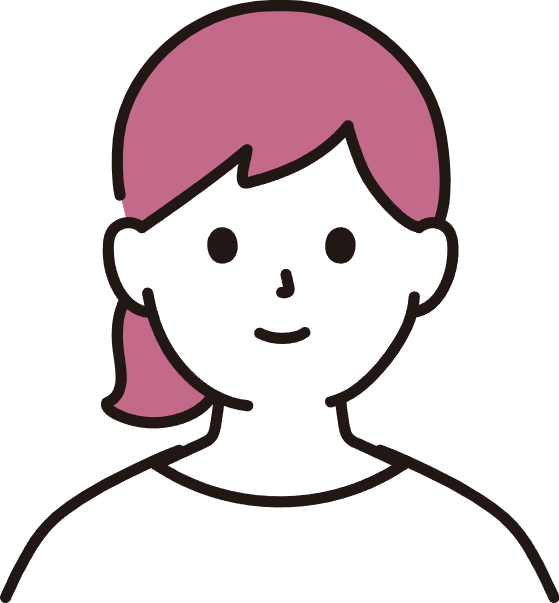
娘は朝が苦手で、何日か欠席してしまったのが後悔です。
個別の先生に欠席分のフォローをお願いしようとしたんですが、夏期後半はいつもの先生の予約がなかなか取れなくて…。体調管理をしっかりできなかったこと、欠席の穴を補うまで時間がかかったことが夏の反省点です。

私は「遊び予定を詰めすぎた」っていう超現実的な後悔です(笑)
お盆にちょっと旅行して帰ってきたら、疲れも出て“夏のペース”を完全に見失ってて。理社の遅れを取り返せないまま夏が終わってしまいました。
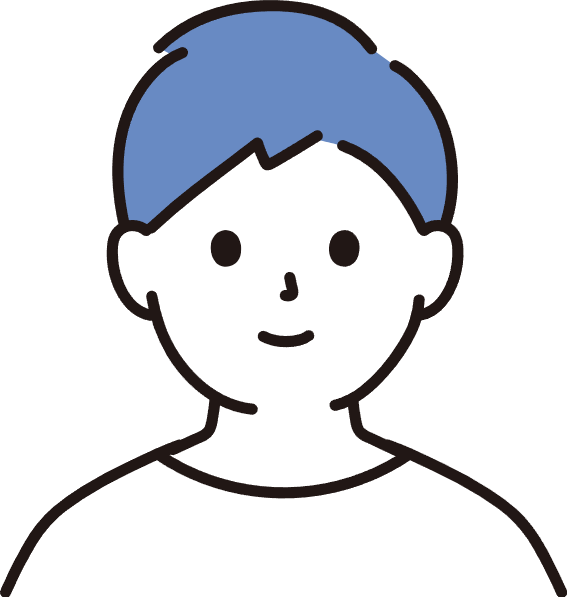
うちの場合は「復習時間の質」をもう少し詰めればよかったなと。
予定は完璧でも、実際の運用で「時間はあるけど集中してない」みたいな日もあって。だから “21時まで復習”よりも、“あと5問だけ解き直す”っていうゴール基準の方が合ってたんじゃないかと、今になって思ってます。
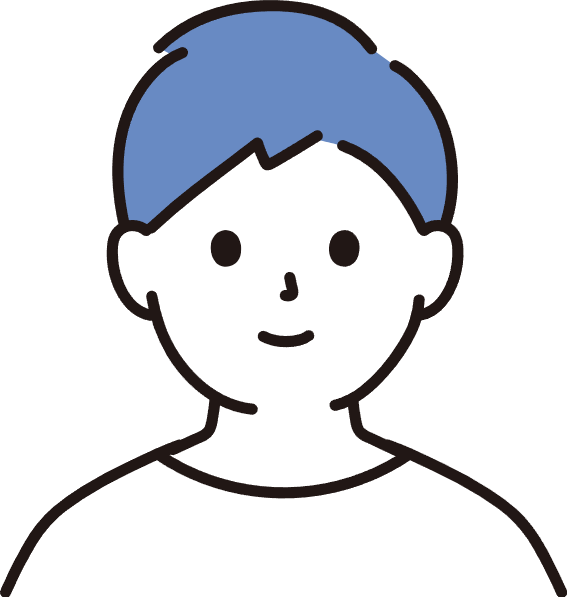
あとは「体調」ですね。夏バテして勉強どころではない日があって、そこも見積もるべきだったなと…。
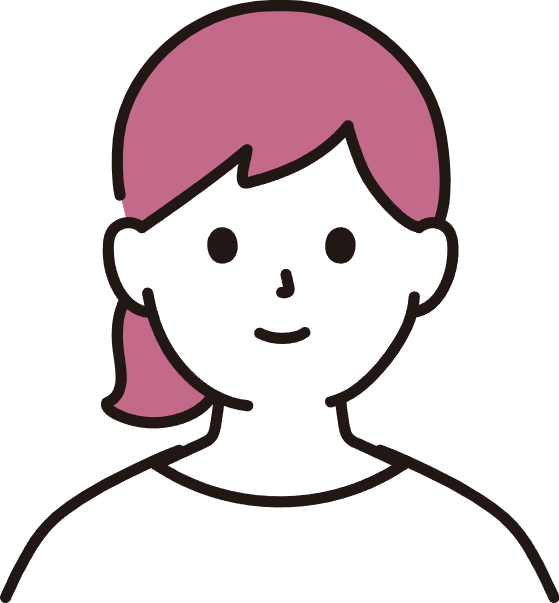
あー分かります!うちも娘が8月前半で体調崩して、3日くらい講習休んだんですけど、「休む=置いていかれる」って親の方がパニックになっちゃって…。
結局その焦りで、私が一番ピリピリしてました…。

夏って“完璧に回す前提”で考えると痛い目見るよね〜(笑)
来年は「多少のズレ込みはある」って前提で、余白も大事にしようと思ってます。

長丁場の夏だからこそ、ある程度の余裕をもってプランニングすることの大切さが見えますね。来年の夏にも生かせそうなお話でした。
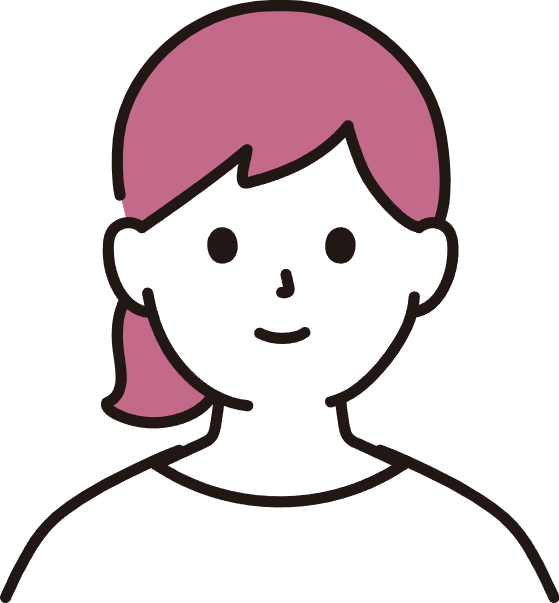
ほんとですね。来年の夏はさらに大切だから、もっと“長く走る”ことを前提に考えなきゃ。「夏を制する者が…」とは言いますけど、燃え尽きたら意味ないですもんね(笑)

うちの子は、朝から塾に通うって経験が勉強習慣の“芯”になって、塾がない日も9時から勉強できるようになりました。それだけでも「やってよかったな」って思えます。
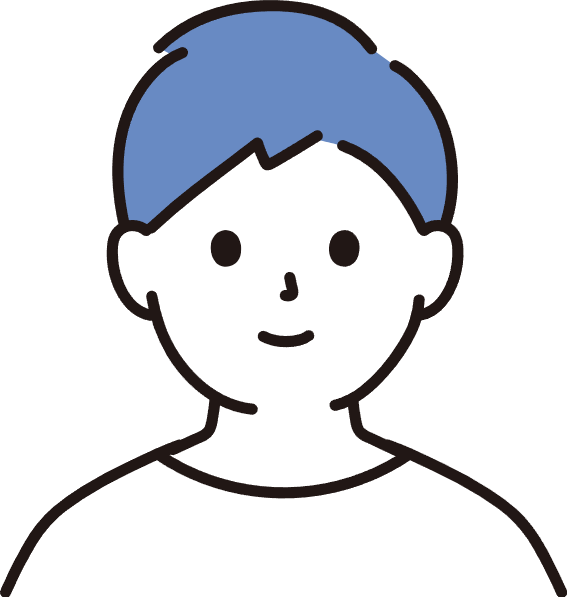
おふたりのお話、すごく共感します。
こうして振り返ると、子どもの意識やペースづくりって、地味だけど一番大きな成果かもしれませんね。だから、予定だけじゃなく“実際どう過ごしたか?”を記録しておくことも、実はすごく意味があるんじゃないかと思っています。
第2回志望校診断サピックスオープンについて

次の質問に移ります。 8月の志望校診断サピックスオープン(以下SO)は、みなさん受験されましたか?
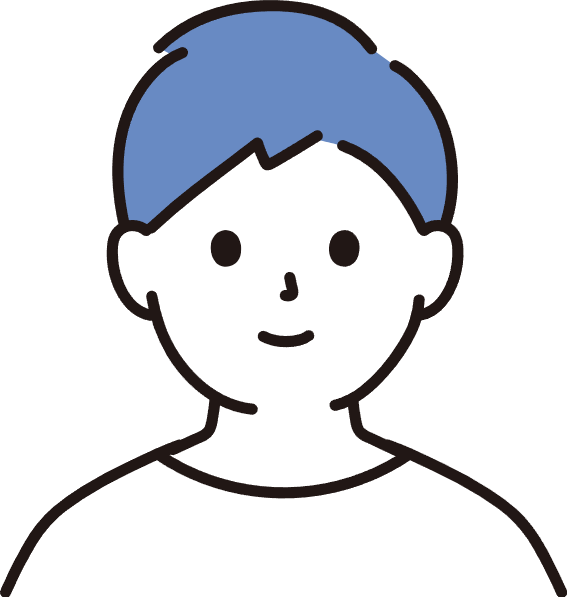
もちろん受けました。受けさせない理由がないと思ってます。
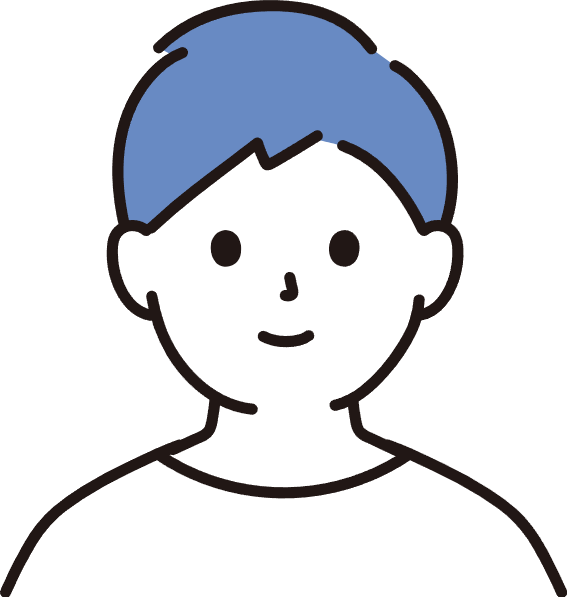
テストは “成績を測るもの”じゃなくて“課題を発見するツール”として捉えていて、今回のSOも国語の記述と理科の知識でハッキリ穴が見えました。
志望校の合格可能性も見ましたけど、あれは夢見がちな親を現実に連れ戻してくれますね(笑)
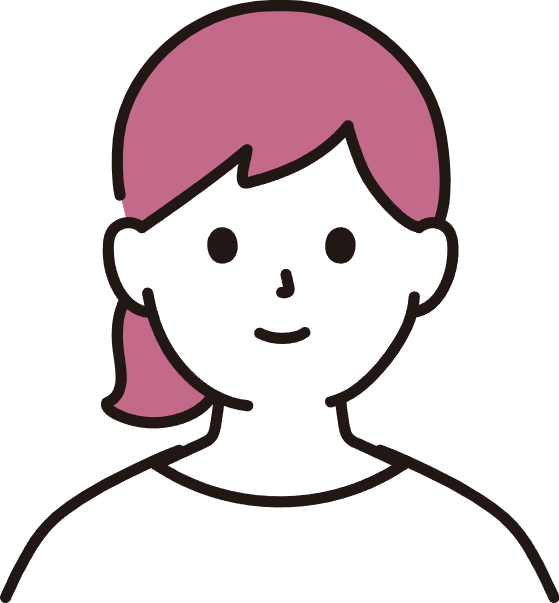
うちは…申し込んだけど受けなかったんです(苦笑)体調崩したのもあって、「模試どころじゃない」って雰囲気だったんですよね。
後で問題を見たら、難しすぎて親子で絶句しました。

うちはSO受けました〜!でも息子にしてみたら「なんか長かった」って印象だけだったみたい(笑)

私は「志望校という言葉に親子で触れること」が大事だと思ってて。息子は志望校まではあまりピンときてないんですけど、校風や入試傾向について親子で話すきっかけにはなったかな。長男(中2)からのアドバイスも珍しく素直に聞いていました。

偏差値は…まぁ、うん(笑) 親のメンタル鍛えられますよね、あれ。
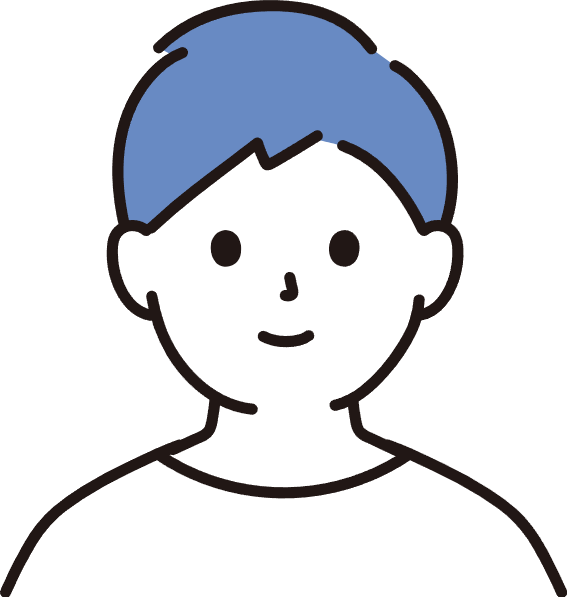
わかります(笑)でも偏差値も、2ヶ月後には全然違うものになる可能性ありますし。「今どこにいて、どう進むか」を冷静に考える材料にすればいいと思ってます。
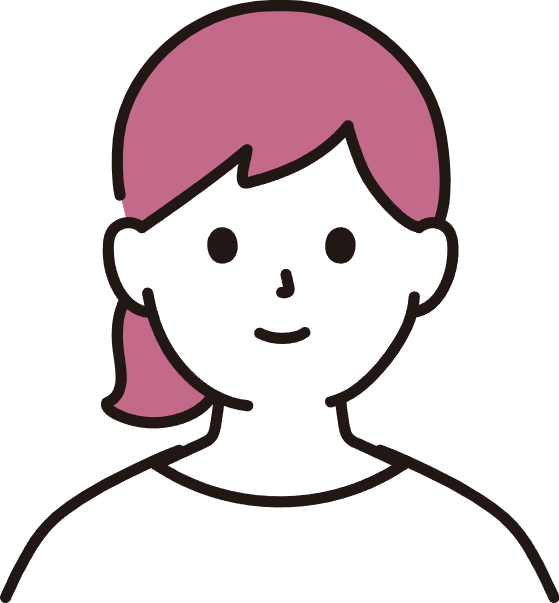
おふたりの話、すごく参考になります…。
うちはまだ“目の前の授業”だけで精一杯なんですけど、模試ってそういう“意識づくり”にもなるんですね。



